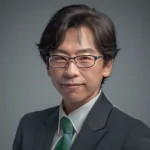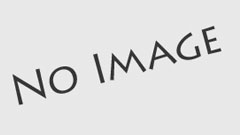電子帳簿保存法は義務じゃない?名古屋の起業家が知るべきDX化の好機
お役立ち情報電子帳簿保存法は義務じゃない?名古屋の起業家が知るべきDX化の好機
名古屋で新たに会社を立ち上げたばかりのあなたへ。「電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)」という言葉を聞いて、何やら難しそうで面倒な義務が増えただけ、と感じていませんか?実はその考え方は、非常にもったいないかもしれません。この記事では、一見すると複雑なこの法律が、実はあなたの会社のバックオフィス業務を劇的に効率化し、経営基盤を強化する絶好のチャンスである理由を解き明かします。読み終える頃には、電帳法への対応が「守りの義務」から「攻めのDX(デジタル・トランスフォーメーション)」へと変わる、新たな視点が得られるはずです。
目次
電子帳簿保存法とは?「3つの区分」で全体像をつかむ
まず大切なのは、電子帳簿保存法(以下、電帳法)の全体像をシンプルに理解することです。この法律は、国税に関する帳簿や書類を電子データで保存するためのルールを定めたもので、大きく3つの区分に分かれています。なぜなら、データの種類や作られ方によって、守るべきルールが異なるからです。具体的には、①会計ソフトなどで最初から電子的に作成する帳簿や書類を保存する「電子帳簿等保存」、②紙で受け取った領収書などをスキャンして画像データで保存する「スキャナ保存」、そして③メールやWebサイトを通じてデータで受け取った請求書などをそのままデータで保存する「電子取引データ保存」の3つです。この中で特に重要なのが、最後の「電子取引データ保存」です。これは、事業規模に関わらずすべての事業者が対象となるため、避けては通れない必須の対応項目なのです。
▼一目でわかる!電子帳簿保存法の3つの区分
| 区分 | 対象となる書類の例 | 対応義務 |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトで作成した仕訳帳・決算書 | 任意 |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った領収書・請求書 | 任意 |
| 電子取引データ保存 | メールで受け取った請求書PDF、Webサイトの領収書 | 義務 |
このセクションの要約
電帳法には「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの区分が存在します。中でも、メールで受け取った請求書などが対象の「電子取引データ保存」は全事業者が対応必須のルールです。この基本を押さえることが、適切な対応への第一歩となります。
なぜ今、対応が必須?避けて通れない「守りの義務」
なぜ対応が必須かというと、現在、メールやネット通販などで受け取った電子データを法律のルール通りに保存することは、すでに全事業者の法的義務となっているからです。2024年1月に猶予期間が完全に終了したため、これから事業を始める、あるいは始めたばかりのあなたの会社は、設立当初からこのルールのもとで経理業務を行う必要があります。この義務の核となる「電子取引データ」の保存を怠ったり、悪質な隠蔽(いんぺい)や改ざん(かいざん)が税務調査で発覚したりした場合、重加算税にさらに10%加重されるという厳しい措置が取られる可能性があります。つまり、これはもはや「新しい規制」ではなく、ビジネスを行う上での大前提。この「守りの義務」を確実に果たすことが、現代の経営におけるスタートラインなのです。
このセクションの要約
電子取引データの電子保存は、すでに全事業者の法的義務です。この「守りの義務」を怠ると、税務調査で発覚した際に重加算税が10%加重されるという厳しいペナルティのリスクがあります。これはビジネスを守るために、まず固めるべき土台と言えます。
「義務」を「チャンス」に変える!攻めのDX経営とは
電帳法への対応を、単なるコストや手間のかかる義務だと捉えるのは早計です。重要なのは、これを会社の業務プロセス全体を見直すきっかけと捉え、経営を強化する「攻めのDX」に転換する視点です。まず、正しく対応するだけで、ペーパーレス化によるコスト削減や業務効率化といった、今すぐ得られる普遍的なメリットがあります。さらに、国は将来に向けた大きな「アメ」も用意しており、2027年からは、この流れがさらに加速します。具体的には、国が定める新基準のシステムで電子取引データを保存すれば、万が一の不正時にも重加算税が10%加重される措置の対象から外れたり、そのシステム利用を要件として個人事業主は最大65万円の青色申告特別控除が受けられたりといった、強力な優遇措置がスタートする予定です。将来の大きなメリットを見据え、今のうちから適切なシステムを選んでおくことが、賢い経営判断と言えるのです。
▼義務をチャンスに!電帳法対応「ビフォーアフター」
| 比較項目 | 守りの義務のまま(最低限の対応) | 攻めのDXへ(将来を見据えた対応) |
|---|---|---|
| ペナルティリスク | 重加算税10%加重のリスクあり | 将来(2027年〜)のリスクを先行して回避できる |
| 業務効率 | 書類探しに時間がかかる。物理的な保管場所も必要。 | データ検索で瞬時に発見。ペーパーレス化が進む。 |
| 税制優遇 | なし | 将来(2027年分〜)、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる可能性(個人事業主) |
このセクションの要約
電帳法対応は、業務効率化のような「現在のメリット」に加え、2027年から始まる「将来のメリット(ペナルティリスクの低減、税制優遇)」もたらします。今から将来を見据えたシステムを選ぶことが、経営を強化する「攻めのDX」に繋がります。
名古屋の起業家が今すぐ始めるべき具体的なアクション
では、具体的に何から始めればよいのでしょうか。以下の3ステップで、今日からアクションを起こしましょう。
- ステップ1:自社の現状を「見える化」する
まずは、自社の業務でどのような「電子取引データ」が発生しているかをすべて洗い出すことがスタートです。例えば、取引先からメールで送られてくるPDFの請求書、Amazon Businessで購入した備品のWeb領収書、クラウドソーシングサイトの支払明細などが挙げられます。どこから、誰が、どんなデータを受け取っているかをリストアップしましょう。 - ステップ2:最適な「道具」を選ぶ
次に、洗い出したデータを「真実性の確保(データが改ざんされていないことの証明)」と「可視性(かしせい)の確保(誰でもすぐに見つけ出し、確認できる状態)」という2つの要件を満たして保存する方法を決めます。ここで重要なのが、将来の優遇措置も見据えたシステム選びです。現行の要件を満たすだけでなく、2027年からの新基準にも対応予定の会計ソフトやクラウドストレージを導入するのが、最も賢い選択です。 - ステップ3:社内の「ルール」を決める
最後に、導入したツールを使いこなすための簡単なルールを決めます。例えば、「請求書PDFはすべて〇〇というフォルダに保存する」「ファイル名は『日付_取引先名_金額』で統一する」といったルールです。この一手間が、後々の業務効率を大きく左右し、「守りの義務」と「攻めのDX」を同時に実現する鍵となります。
このセクションの要約
まずは自社で扱う請求書や領収書などの「電子取引データ」をすべて把握することから始めましょう。次に、それらを「改ざんできず、すぐ探せる」状態にするため、電帳法対応の会計ソフトを導入するのが最も確実です。これが、具体的なアクションの第一歩となります。
この記事のまとめ
電子帳簿保存法は、単に守るべき義務ではなく、業務効率化や税制優遇といったメリットを享受し、会社の経営基盤を強化する「攻めのDX」の好機です。リスクを回避しつつ、デジタル化の恩恵を最大限に活用する視点が重要になります。
よくあるご質問(FAQ)
- 私は個人事業主ですが、電帳法への対応は必要ですか?
- はい、必要です。電子帳簿保存法は、法人か個人事業主かを問わず、すべての事業者が対象となります。特に、メールやウェブサイトで請求書や領収書を受け取っている場合、その「電子取引データ」の電子保存は義務となります。
- 2027年からの話なら、今すぐ高いシステムを導入する必要はないのでは?
- 良い質問です。必ずしも最高機能のシステムを今すぐ導入する必要はありません。しかし、経理システムは一度導入すると乗り換えが大変です。そのため、最初から将来の法改正(2027年の優遇措置など)に対応を表明している信頼できるベンダーのサービスを選ぶことが、長期的に見てコストと手間を削減する賢い選択と言えます。
- 紙で受け取った請求書や領収書はどうすればよいですか?
- 紙で受け取った書類は、これまで通り紙のまま保存するか、もしくは「スキャナ保存」の要件を満たして電子データ化するかのどちらかを選択できます。「スキャナ保存」を行う場合は、タイムスタンプの付与や解像度の確保など、一定のルールを守る必要があります。ただし、義務化されているのは「電子取引データ」の電子保存であり、紙書類の電子化は任意です。
参考文献
投稿者プロフィール