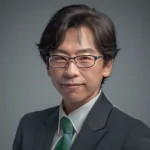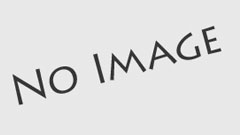クラウド会計の罠?!電帳法対応とデータ管理のツボ
お役立ち情報
近年、経理業務はクラウド化と法改正の波に直面しています。この記事では、電子帳簿保存法対応の基本から、クラウド会計ソフト利用時の思わぬ落とし穴、特にデータの長期保存に関する注意点、そして自社に最適なサービスを選ぶための総合的な視点まで、初心者にも分かりやすく解説。あなたの会社の経営が「一段上」の安心感を得るためのヒントがここにあります。
クラウド時代の経理・税務と電子帳簿保存法の基本
近年、働き方が大きく変わる中で、経理・税務の世界もまた、電子帳簿保存法 (でんしちょうぼほぞんほう) という大きなルール変更への対応が求められています。この法律は、紙で保存していた帳簿や書類を電子データで保存することを認めるものですが、ただデータ化すれば良いというわけではありません。特に重要なのが、そのデータが「本物である」と証明し、「後から改ざんされていない」ことを示す「真実性の確保」です。これを怠ると、せっかく電子化したデータが税務調査などで認められない可能性もあり、企業にとっては大きなリスクとなり得ます。そのため、まずはこの「真実性の確保」が何を意味するのかを正しく理解することが、クラウド時代の経理DX (デジタル トランスフォーメーション) の第一歩と言えるでしょう。 では、具体的にどうすればデータの「真実性の確保」ができるのでしょうか。主な方法としては、まず「認定タイムスタンプ」の付与が挙げられます。これは、その時刻にその文書が存在し、それ以降改ざんされていないことを第三者機関が証明する刻印のようなものです。最近では、WPS Cloudのようなオフィスソフトにもこの機能が搭載され始めています。次に、訂正・削除の履歴が残る、あるいはそもそも訂正・削除ができない仕組みのシステムを利用することです。多くのクラウド会計ソフト、例えばfreee (フリー) やマネーフォワードなどは、この要件を満たすよう設計されています。最後に、これらのシステム導入が難しい場合でも、「事務処理規程」という社内ルールを整備し、それに沿った運用を徹底することでも対応が可能です。どの方法が自社に適しているかを見極めることが肝心です。「クラウド時代の経理・税務と電子帳簿保存法の基本」の要点
電子帳簿保存法対応の核心は「真実性の確保」にあり、タイムスタンプや履歴管理システム、事務処理規程といった手段でこれを実現します。自社の状況に合わせた適切な方法の選択が、法令遵守と業務効率化の両立への鍵となります。クラウド会計ソフト活用のポイントと注意点
クラウド会計ソフトの導入は、経理・税務業務の効率化や法対応の観点から非常に有効ですが、その機能を最大限に活かすためには正しい理解と運用が不可欠です。例えば、freeeやマネーフォワードといった主要なクラウド会計ソフトは、多くの場合、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会 (JIIMA (ジーマ)) の認証を取得しており、電子帳簿保存法の要件を満たすように作られています。これにより、ユーザーは比較的容易に法対応を進めることが可能です。しかし、重要なのは、ソフトを導入しただけで安心してしまうのではなく、自社の業務フローに合わせて適切に設定し、日々の取引データを正確かつタイムリーに入力・管理していくことです。そうでなければ、せっかくのシステムも宝の持ち腐れとなりかねません。 そして、クラウド会計ソフトを利用する上で意外と見落としがちなのが、サブスクリプション契約を解約した後のデータの取り扱いです。電子帳簿保存法では、原則として帳簿書類を7年間(場合によっては10年間)保存する義務があります。クラウドサービスの場合、有料プランを解約すると、無料プランに移行して一部機能制限のもとでデータ閲覧が継続できるケース(例:freeeの一部)もあれば、事前にユーザー自身で全データをエクスポートしておかないと、後からアクセスできなくなる、あるいは閲覧のみで編集や追加ができなくなるケース(例:マネーフォワードのサービスやプランによる)も存在します。長期的なデータ保存義務をどう果たすのか、契約前にサービスごとの規約をしっかり確認し、解約後の運用まで見据えた計画を立てておくことが、将来のトラブルを避けるために極めて重要になります。「クラウド会計ソフト活用のポイントと注意点」の要点
クラウド会計ソフトは法対応の強力な味方ですが、導入後の適切な運用と、特にサブスク解約後のデータ長期保存計画が不可欠です。サービスごとの特性を理解し、7年以上の保存義務を見据えた対策を講じましょう。自社に最適なサービスを選ぶための総合的視点
クラウドサービスを選ぶ際、単に機能の多さや料金だけで判断してしまうと、後で「こんなはずではなかった」という事態に陥りかねません。自社の規模や業種、そして将来の展望まで含めた多角的な視点から、最適なパートナーとなるサービスをじっくりと見極めることが、経理DX成功の分かれ道となります。例えば、機能面では、単に電子帳簿保存法に対応しているかだけでなく、自社の取引形態や必要な帳票の種類、他システムとの連携性などを具体的に確認する必要があります。JIIMA認証を取得したシステムであれば、履歴管理と検索機能が揃い、ワンストップで法要件を満たせるため運用が比較的楽になるというメリットがあります。 運用コストについても、初期費用や月額料金だけでなく、オプション機能の追加料金、さらには従業員が新しいシステムに慣れるまでの学習コストや日々の運用にかかる人的リソースまで考慮に入れる必要があります。中小企業や個人事業主の方で、既存のスキャン・PDF運用を活かしつつコストを抑えたい場合には、認定タイムスタンプ単体の導入も有効な選択肢となり得ます。また、システム導入のコストや手間を極力かけたくない、あるいはごく小規模な事業運営である場合には、社内で「事務処理規程」をしっかりと整備し、それに則った運用を徹底するという方法も、法律上認められた現実的な選択肢の一つです。これは、法対応のコストを最小限に抑える上で検討に値するでしょう。 そして、サービスの「使いやすさ」は日々の業務効率に直結する重要な要素です。直感的に操作できるインターフェースか、マニュアルやサポート体制は充実しているか、といった点はデモやトライアル期間を利用して実際に触れて確認することをお勧めします。さらに、前章でも触れた「サブスクリプション終了後のデータ主権と長期保存ポリシー」は、サービス選定における最重要チェックポイントの一つと言っても過言ではありません。解約後もデータにアクセスできるのか、エクスポートは容易か、そして何より7年~10年という法定保存期間をどのように担保できるのか。これらの点を契約前に徹底的に確認し、自社のデータを確実に守り、将来にわたって法令を遵守できる体制を築くことが求められます。「自社に最適なサービスを選ぶための総合的視点」の要点
最適なクラウドサービス選びは、機能、コスト、使いやすさ、そしてデータ主権と長期保存ポリシーの総合評価が鍵です。自社のニーズを明確にし、デモ活用や規約確認を徹底して、将来を見据えた選択を行いましょう。この記事のまとめ
電子帳簿保存法対応ではデータの「真実性確保」が鍵。クラウド会計ソフト利用時は適切な運用、解約後のデータ管理、そして機能・コスト・使いやすさ・データ主権を総合的に評価し選択することが重要です。FAQ:クラウド会計と電子帳簿保存法に関するよくある質問
- Q1: 電子帳簿保存法って、具体的に何が変わったのですか?
- A1: 一言でいうと、これまで紙での保存が原則だった国税関係の帳簿や書類について、一定の要件を満たせば電子データで保存することが広く認められるようになりました。特に、電子取引のデータは電子データのまま保存することが義務化されるなど、ペーパーレス化を大きく進める内容となっています。
- Q2: タイムスタンプは必ず付けないといけないのですか?
- A2: スキャナ保存の場合や、訂正削除の履歴が残らないシステムで電子取引データを保存する場合などには、原則としてタイムスタンプの付与が必要です。ただし、訂正削除履歴が残るシステムを利用する場合や、発行者側でタイムスタンプが付与されている場合など、一定要件を満たせば不要となるケースもあります。
- Q3: クラウド会計ソフトの無料プランでも電帳法に対応できますか?
- A3: サービスやプランによって機能が異なります。多くの有料プランでは電帳法の要件を満たす機能が提供されていますが、無料プランでは機能が制限されている場合があります。特にデータの保存期間や訂正・削除履歴の確保、検索機能などが要件を満たせるか、各ソフトの提供元にご確認ください。
- Q4: サブスクを解約したら、データはすぐに消えてしまうのですか?
- A4: サービス提供会社の方針や契約内容によります。解約後も一定期間は閲覧可能であったり、無料プランに移行してデータが保持されたりする場合もあれば、事前のデータエクスポートが必須で、それを怠るとアクセスできなくなる場合もあります。必ず契約前に確認し、必要なデータを7年~10年間保存できる体制を整えることが重要です。
参考文献
- 国税庁「電子帳簿保存法 電子帳簿等保存制度特設サイト」
- JIIMA公式サイト
- freee ヘルプセンター | 電子帳簿保存法の概要・手続について
- マネーフォワード クラウドサポート | 電子帳簿保存法への対応について
- WPS Cloud 公式サイト | 電子帳簿保存法対応情報
クラウド会計の導入から日々の運用、そして法改正への対応まで、専門家と一緒に解決しませんか。
投稿者プロフィール