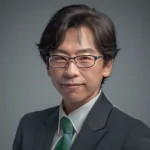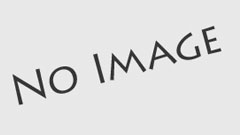JPYCとは?税理士が経理視点で解説|JPYC EXで発行・償還と実務ポイント【2025/10/27正式発行】
お役立ち情報August 18, 2025 (最終更新:2025年10月27日)
【最新動向】JPYCが正式発行を開始、公式プラットフォーム「JPYC EX」も稼働
2025年10月27日13:00(JST)、JPYC株式会社が日本円ステーブルコイン「JPYC」の正式発行を開始し、発行・償還を受け付ける公式プラットフォーム「JPYC EX」を公開しました。対応チェーンはAvalanche / Ethereum / Polygon(順次拡大予定)。本記事は中小企業の経理実務に役立つ観点で、JPYCの仕組みと実務ポイントを解説します。
これまで1,000件以上の創業相談を受けてきた税理士の視点から、多くの中小企業経営者が直面する課題を見てきました。特に、「ネットショップの返品対応で、振込手数料が利益を削っている」「日々の入金消込に時間がかかりすぎる」といった声は後を絶ちません。こうした地味ながらも深刻な悩みを解決する可能性を秘めているのが、法制度に位置づけられたデジタル円「JPYC」です。この記事では、専門用語が苦手な方でも理解できるよう、以下の3つの問いに順番にお答えしていきます。
- JPYCの安全な仕組みとは何か?
- 中小企業にとっての具体的なメリットは何か?
- 経理実務での活用例と、導入前の注意点は何か?
目次
JPYC(ジェーピーワイシー)とは?:仮想通貨とは違う「安心なデジタル円」
JPYCは、近年注目される「ステーブルコイン(Stablecoin)」の一種です。しかし、「コイン」と聞くと、値動きの激しいビットコインのような暗号資産(仮想通貨)を想像して不安になるかもしれません。結論から言うと、JPYCは投機目的の暗号資産とは全く異なる、安全性を重視した仕組みで設計されています。
第一に、原則として「1 JPYC = 1円」での発行・償還が可能な点です。発行残高に対し同額以上の日本円(預貯金および国債)を保全する設計で、利用者は円ベースの価値で扱えます(市場環境によって二次市場価格が短期的にわずかに変動する可能性はゼロではありません)。
第二に、その安全性は法律によって裏付けられている点です。金融庁の監督のもと、2023年6月に施行された改正資金決済法により、JPYCのようなステーブルコインは「電子決済手段」として法的に明確に定義されました。
そして第三に、発行できるのが金融庁に登録された特定の事業者(※)に限られている点です。これにより、誰でも発行できる一部の暗号資産とは一線を画し、信頼性が担保されています。
(※)発行主体は事業モデルによって「資金移動業者」「信託会社」「銀行」の3種類に分かれます。JPYCは資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00099号)として登録済みで、2025年10月27日に正式発行を開始しました。
※本記事でいう「JPYC」は、資金決済法上の電子決済手段としてのJPYCを指し、従来のJPYC Prepaid(前払式支払手段)とは異なります。
JPYC EXでの基本フロー(発行/償還・KYC・対応チェーン)
- 発行:JPYC EXで発行予約→銀行振込→登録ウォレットへJPYCが発行
- 償還:JPYC EXで償還予約→指定アドレスへJPYC送付→登録出金口座へ円で払い戻し
- KYC:マイナンバーカードのJPKI(公的個人認証)で本人確認
- 対応チェーン:Avalanche / Ethereum / Polygon(順次拡大予定)
※JPYC EXは、JPYCの発行・償還を受け付ける公式プラットフォームです。
※オンチェーン送付(ウォレット間の送受信)は24時間365日ですが、発行・償還は銀行の入出金等の手続に依存します。
中小企業にとっての3つのメリット
JPYCが安全な仕組みであることは分かりました。次に、中小企業の経営者にとって最も重要な「で、結局うちの会社にどんな得があるの?」という問いにお答えします。メリットは、「コスト」「効率」「スピード」の3つの側面に集約されます。
- コスト削減:
大きなメリットは、決済手数料の削減です。一件あたり数百円かかることもある銀行振込手数料は、取引が増えるほど重い負担となります。対して、JPYCの送金にかかる手数料は、銀行振込と比較して低く抑えられるように設計されており、特に少額の返金や支払いが頻繁に発生するビジネスでは、その差は無視できません。(※ネットワーク手数料等は別途発生します。条件によっては逆転するケースもあります) - 経理の効率化:
JPYCでの取引は、ブロックチェーン(分散型台帳)上にデータが記録されるため、改ざんが困難で透明性が高いという特徴があります。今後、取引データが会計ソフトとAPI連携(※システム同士を繋ぐ仕組み)することで、入金消込や帳簿付けの多くが自動化されることが期待されています。 - スピードアップ:
銀行振込は、銀行の営業時間に左右され、着金まで数時間から翌営業日かかることも珍しくありません。しかし、JPYCはインターネット上で直接やり取りするため、原則として24時間365日、取引が迅速に完了します。これにより、資金繰りの見通しが立てやすくなるだけでなく、顧客への返金対応なども迅速に行えます。(※システムのメンテナンス時間や、取引の承認時間により、即時でない場合もあります)
JPYCがコスト・効率・速度の面でメリットをもたらす可能性を解説しました。しかし、これらはまだ抽象的です。次章では、より具体的な業務シーンに落とし込んで見ていきましょう。
【具体例】経理の実務はどう変わる?
ここでは、特にメリットを享受しやすい2つの業務シーンを例に、JPYC導入前後の変化を見てみましょう。
- ケース1:ネットショップの返品返金
- 【導入前】 顧客から返品依頼があり、指定口座に銀行振込で返金。毎回振込手数料が発生し、経理担当者は振込作業と記帳に時間を取られる。
- 【導入後】 顧客のウォレット(電子財布)に、JPYCで迅速に返金。手数料は銀行振込より低く抑えられ、取引記録も自動で残るため、経理の手間が大幅に削減される。
- ケース2:日々の入金消込
- 【導入前】 複数の顧客からの売上入金を、銀行の取引明細と一件ずつ照合。同姓同名や振込名義の間違いがあると、確認に多大な時間がかかる。
- 【導入後】 JPYCでの支払いは、誰から誰への取引かがデータとして明確に残る。将来的には会計ソフトと連携し、売掛金の消込作業がほぼ自動で完了するようになる。
新しい決済手段、専門家と一緒に考えませんか?
JPYCのような新しい技術の導入は、経理を効率化する大きなチャンスです。しかし、税務上の扱いや会計ソフトとの連携など、専門的な判断が必要な場面も。私たち専門家が、あなたの会社に最適な導入プランを一緒に考えます。
まずは無料で相談してみる具体的な業務シーンでJPYCがどう役立つかを見てきました。しかし、どんな新しい技術にも限界はあります。最後に、導入前に必ず知っておくべき注意点を解説します。
導入前に知っておくべき注意点と限界
JPYCは大きな可能性を秘めていますが、現時点では「魔法の杖」ではありません。導入を検討する際には、以下の3つの限界点を冷静に認識しておく必要があります。
- 普及するかはまだ未知数:
2025年10月27日に正式発行・運用が始まりましたが、自社が導入しても、取引先や顧客が対応していなければ利用は広がりません。段階的な普及を前提に、用途と相手先を見極めて導入しましょう。 - 税務上の扱いは要確認:
JPYCは法的に「電子決済手段」と位置づけられましたが、法人税や消費税の計算において、具体的な会計処理や税務上の取り扱いについては、今後国税庁から詳細な指針が示されるのを待つ必要があります。自己判断での処理は危険です。(※企業会計基準委員会(ASBJ)から実務対応報告第45号が公表されていますが、これは暫定的な取り扱いであり、今後の動向を注視する必要があります。会計処理は当面、同報告に沿った取り扱いの参照が有効です。) - システム連携の現状:
会計ソフト等との完全な自動連携は、まだ「期待される未来」の段階です。まずはJPYC EXの運用範囲でできること(発行・償還・送受信)を把握し、段階的にワークフローへ組み込みましょう。
用語整理:JPYC(電子決済手段) と JPYC Prepaid(前払式支払手段)
- JPYC Prepaid:2025年5月30日13時で新規発行を終了(最終入金18:00)。6月1日0時以降は発行なし。現金への償還は現時点で予定なし。
- JPYC(電子決済手段):資金移動業者登録(関東財務局長 第00099号)に基づき2025年10月27日から正式発行。発行・償還はJPYC EX経由で手続き。
両者は別のトークンで、当社での相互交換は受け付けていません(混同に注意)。
「JPYCって怪しい?」その疑問に、税理士が経理視点でお答えします。JPYCは国の法制度に基づいた安全なデジタル円であり、中小企業の「コスト削減」「経理効率化」に貢献する可能性があります。ネットショップの返金手数料削減などの具体例から、その仕組みと注意点をわかりやすく解説しました。
よくある質問
※以下の回答は、金融庁の公表資料や発行元の公式発表など、公開情報を基に専門家の視点から解説したものです。
Q1. JPYCは、SuicaやPayPayのような電子マネーと何が違うのですか?
A1. 最も大きな違いは、その技術的な背景と相互運用性です。電子マネーは発行事業者の管理する閉じたシステムで機能しますが、JPYCはブロックチェーンという開かれた技術を基盤としています。これにより、特定のサービスに縛られず、世界中の誰とでも直接やり取りできる可能性を秘めています。
Q2. 結局のところ、本当に安全なのでしょうか?
A2. はい、法律と仕組みの両面から高い安全性が確保されています。2023年施行の改正資金決済法に基づき、発行者は利用者の資金を保全し、同額の円での償還に応じる枠組みです。万が一発行者が破綻しても、利用者の資産は法的に守られるスキームが整備されています。ただし、利用者自身によるパスワード管理といった基本的なセキュリティ対策は別途必要です。
Q3. いつから本格的に使えるようになりましたか?
A3. 2025年10月27日13:00(JST)から正式発行が始まりました。発行・償還は公式プラットフォーム「JPYC EX」で受け付けています。
Q4. JPYCの価値は、常に安定して「1 JPYC = 1円」なのでしょうか?
A4. 法律上の枠組みに基づき、1円での償還が可能です(発行残高以上の裏付け資産を保全)。実務上はJPYC EXを通じて償還手続きを行います。なお、二次市場で売買される際は、需給によって一時的に価格がわずかに変動する可能性はあります。
参考資料
免責事項
本記事では、JPYCの会計上の概要を解説しており、個別の税務申告における具体的な仕訳や計算方法、またはJPYCを投資対象として評価するものではありません。税務判断や投資判断は、必ず専門家にご相談ください。
あなたのビジネスを、次のステージへ
本記事で解説した内容は、あくまで一般的な情報です。新しい技術の導入や税務に関する判断は、必ず専門家にご相談ください。当事務所では、クラウド会計の導入支援から、新しい決済手段に関するご相談まで、企業のDXをサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。
専門家に無料で相談する投稿者プロフィール